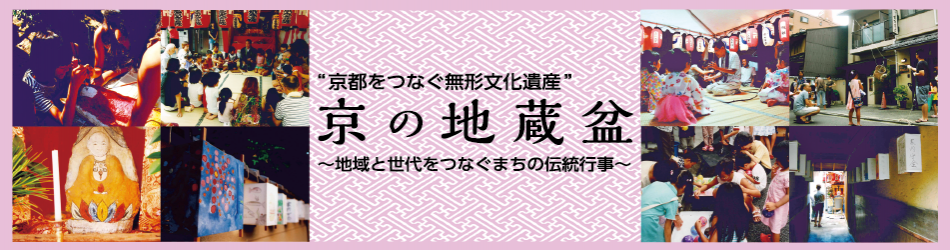「京都をつなぐ無形文化遺産」という制度は、国や京都府へ申請して認めてもらう文化遺産ではなく、市民が地域と世代をつなぐ伝統として選ぶ文化遺産である。私は大変気に入っており、あちこちで講演を頼まれて話す機会に、この制度の宣伝をしている。そしてこの度、この制度による文化遺産の一つとして地蔵盆を選ぶお手伝いができたことを嬉しく思っている。
いま地蔵盆と呼んでいる行事は、江戸時代、明治半ばまで「地蔵祭」とか「地蔵会(じぞうえ)」と呼んでいた。この行事は町の構造と深く結びついている。明治以前、京都の町は、道の両側の住戸の集合として成り立っていた。治安のため、両端には木戸があって、木戸番がいた。道は住戸の延長で、仕事の場としても使われ、子ども達にとっては、大人たちの目の行き届く安全な遊び空間だった。昼間は通行できるけれど、一定時間になると木戸が閉められ、それから後はくぐり戸からしか出入りできなかった。
木戸の手前の町内の端に、お地蔵さんの祠(ほこら)と、ちり溜めが置かれていた。町内の端、となりの町内との境近くにあったという意味では、ムラ境にある賽の神と同じようなものだった。そして町内の人たちは、お地蔵さんに町内の安全をお祈りしていた。
いま、地蔵盆のときに、あまり通行の妨げにならないような道路を一時通行止めにして、地蔵盆のテントを張ったりするのはその名残である。
明治5年に木戸が廃止され、京都の道路を拡幅して近代都市にするためには、お地蔵さんの祠は邪魔だから壊せということになってしまった。お地蔵さん受難の時代である。さいわい地蔵盆は明治の半ばに復興して盛んになる。京都の市民が活気を取りもどした証拠だろう。学校教育が普及して、同年齢で組織されるようになっても、長い夏休みには、地域の異年齢の遊びの集団が復活することとも無関係ではないだろう。
今後、地蔵盆はどういうふうになっていくのだろうか。時代の変化に合わせてたとえ少しばかり姿が変わっても、とにかく続いていくことが大事だ。昔のやり方を復活するばかりが正しいとは思わないけれども、昔のやり方がどうだったかを知って、その通りやってみようという町内があってもおもしろいと思う。(談)
山路 興造(京都をつなぐ無形文化遺産「京の地蔵盆」審査会委員、京都市文化財保護審議会委員)