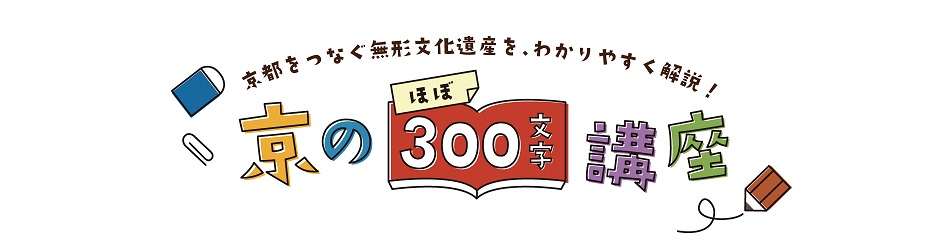「お月見」の季節になりましたね。お月見とは「観月(かんげつ)の宴(うたげ)」のことで、中国から伝わり平安期の宮中で盛んに行われていました。
一般の人たちには、秋の恵みに感謝する収穫祭として親しまれるようになったそうで、豊作祈願として芋(里芋)をお供えしたことから旧暦8月の十五夜(中秋の名月)のことを「芋名月」と呼びました。さらに、旧暦9月の十三夜には、食べ頃になった栗や枝豆をお供えして「栗名月」・「豆名月」と呼び、それぞれの名月を祝っていたんですよ。
京都の十五夜のお供えで、里芋のカタチに似せた月見団子がよく見られるのは、そんな理由だったのですね。里芋の皮の部分に小豆を使うことで、邪気も祓うとか。今年のお月見、あなたはどっちのお団子をお供えしますか?